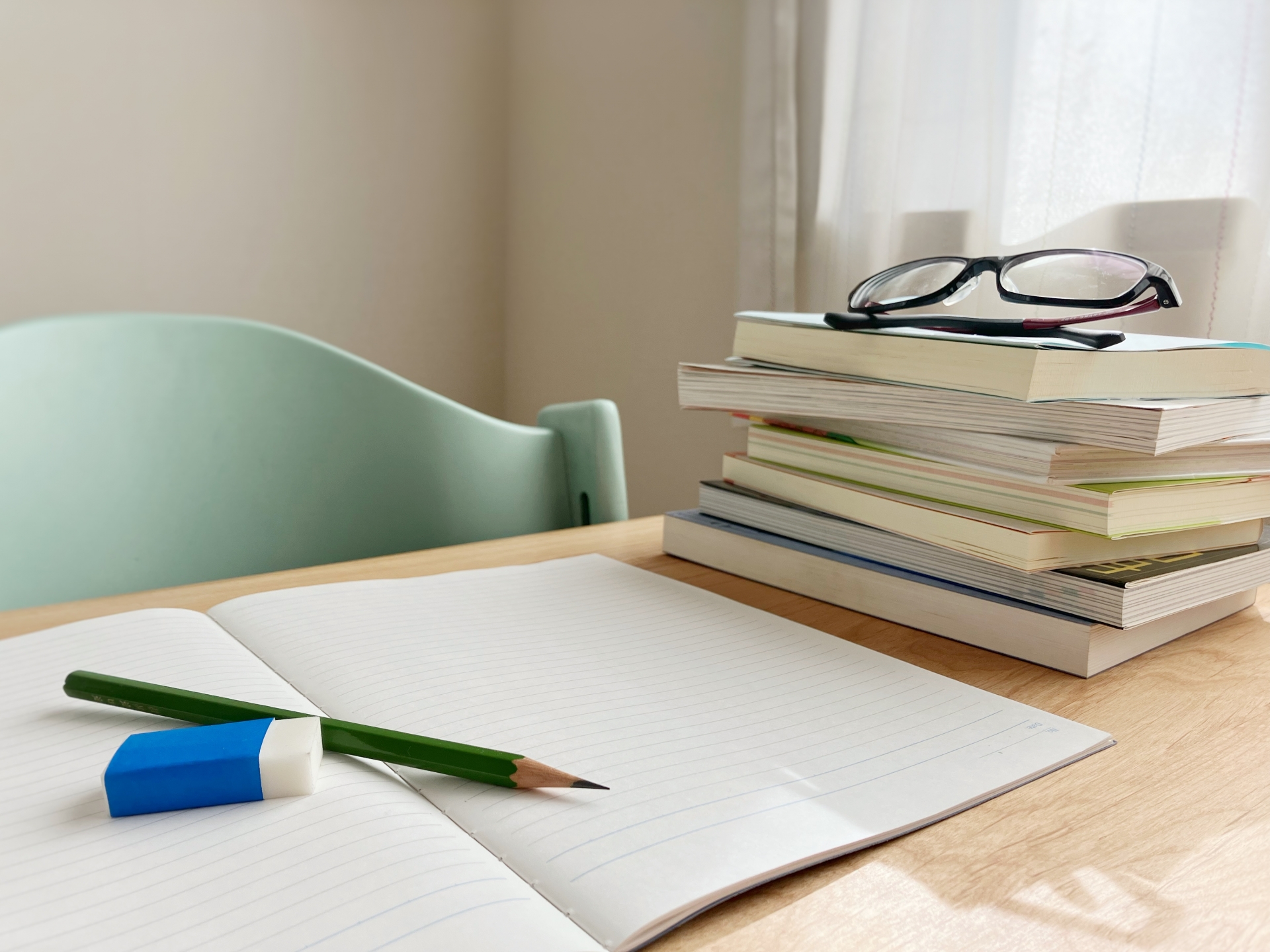日本語には「づらい」と「ずらい」という似ているが異なる表現が存在し、これらの正しい使い分けについて疑問を持つことが多いです。
例えば、「生きづらい」や「生きずらい」、「わかりづらい」や「わかりずらい」、「行きづらい」や「行きずらい」など、どちらの表現が適切なのか迷う場合があります。
この記事では、以下の内容を詳しく解説します。
- 「づらい」と「ずらい」の使い分け
- これらの表現が持つ意味の違い
これらのポイントを踏まえて、両表現の正しい使用方法を明確にします。
「づらい」の適切な使用法

「づらい」は日本語で正しい表現とされています。
たとえば、「行きづらい」という表現を見てみましょう。これは「行く」と「つらい(辛い)」が結合して形成された言葉で、何かを行うことが困難である状態を示しています。
この文脈では、「ずらい」という表現は適切ではなく、また、「つらい」を「ずらい」に置き換えることも一般的ではありません。
「づらい」と「ずらい」の使い分け
「やりずらい」と「やりづらい」のどちらを使用すべきか迷う場合、単語を分けて考えることが助けになります。
「やりづらい」は「やる」と「つらい(辛い)」の組み合わせで成立しており、この形の場合「づらい」の使用が適切です。
また、「つらい」と「からい」が同じ「辛い」という漢字で書かれることは、同一漢字が異なる読みを持つ一例です。
「づらい」と「ずらい」の区別

「づらい」と「ずらい」は同じ意味を持つ場合が多く、日本語において「づ」と「ず」の音が区別されないことが一般的です。
たとえば、「これ読みづらいな〜」と「これ読みずらいな〜」と発言した際の発音の違いを明確に捉えるのは困難です。
理論的には「づ」と「ず」どちらを用いても誤りではないものの、慣例的には「〇〇+辛い」という組み合わせの場合、「づらい」と表記することが多くなっています。
「ずらい」と入力するとどうなる?
パソコンで「ずらい」とタイプすると、多くの場合自動的に「づらい」に変換されます。この誤入力はあまり一般的ではありません。
しかし、スマートフォンや携帯電話では自動変換がうまく機能しないことがあり、「ずらい」が「づらい」に変わらない場合もあります。
このため、ソーシャルメディア上では「ずらい」という表記が増えており、多くの人が「づらい」よりも「ずらい」の方が自然に感じる傾向があります。
【まとめ】「ずらい」と「づらい」、どちらを使用すべきか?
「ずらい」と「づらい」のどちらを使うか迷った際は、「づらい」を選ぶことが一般的に推奨されます。
「ずらい」を使用しても文法的な誤りではありませんが、慣用的には「づらい」が広く使われています。
ただし、SNS上での「ずらい」の使用頻度が高まっているため、将来的には「ずらい」がより普及する可能性も考えられます。