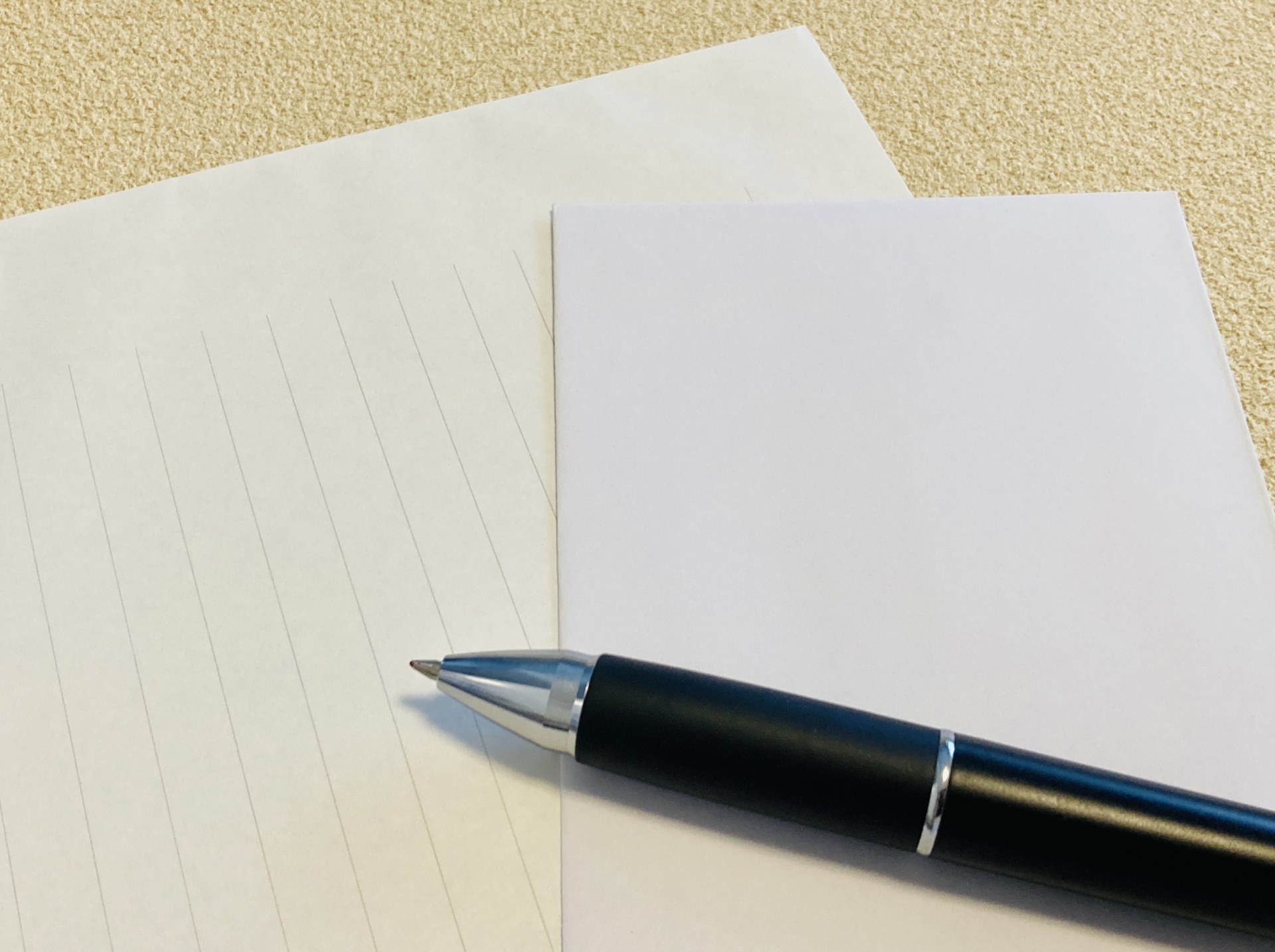教育実習後のお礼状には、白色無地の長形4号二重封筒を使用するのが適切です。
コストパフォーマンスに優れたマルアイ製の封筒がおすすめで、100枚入りなので大学の仲間と共有することも可能です。
お礼状は教育実習を終える際の重要な一環であり、封筒の選び方や宛名の書き方はマナーとして非常に重要です。
礼儀作法は秩序と人間関係の維持に不可欠で、信頼関係の構築に役立ちます。感謝の気持ちを込めたお礼状も、マナーが不適切だと不快な印象を与えかねません。
この記事では、封筒選びや宛名の書き方の正しいマナーを図解付きで詳しく説明しています。
正しいマナーを学び、印象的なお礼状を作成しましょう!
教育実習のお礼状に適した封筒の選び方
教育実習のお礼状には、白色無地の長形4号の二重封筒を選ぶのが望ましいです。これらはコストが低く、大型100円ショップなどで扱っている場合が多いので、探してみることをお勧めします。
では、なぜお礼状に二重封筒が推奨されるのでしょうか。二重封筒は、内部の書類が外から見えないように設計されています。これはプライバシーの保護と送り手の配慮を示し、公式な場や目上の人への送付にふさわしいとされています。
白封筒は正式な手紙やフォーマルな相手に対して使用するのが一般的です。一方で、茶封筒はより事務的な書類に用いられることが多いです。したがって、お礼状ではフォーマルな白封筒を選ぶのが適切です。
このため、白色無地の二重封筒を選ぶことが、教育実習のお礼状を送る際の正しいマナーとされています。
宛名の書き方を図解で学ぶ
これからは宛名の正しい書き方を図を用いて詳しく説明します。
宛名の書き方(表面)
- 郵便番号の下に住所を一字下げて記載します。
- 学校名は正式名称で記述し、例えば「◇◇◇◇高等学校」と具体的に書きます。
- 学校名と先生の名前は住所よりも大きく目立つように一字下げて記述します。
- 先生の氏名は間を空けて書き、校長以外に宛てる場合は、クラスと先生の名前を「三年二組担任 ○○ ○○先生」と具体的に書きます。
重要なのは、学校名をその正式な名称で記述することです。
表面の記入が終わったら、封筒の裏面にも進みます。
宛名の書き方(裏面)
- 郵便番号の最後の数字の下あたりに一字下げて住所を記載します。
- 自分の大学名と学部、そして教育実習生であることを明記します。
- 大学名と氏名は住所よりも大きく一字下げて書きます。
- 送付する日付を封筒の左上端に記載します。
- のり付け後、封筒の蓋と封筒の境界に封字「〆」を記入します。
大学名と学部の記載は忘れがちですが、特に教育実習生を多く受け入れる学校では重要です。これにより、住所と名前だけでは思い出せない場合でも、誰であるかを思い出しやすくなります。
また、封筒に封字を記入するのは、中身が未開封であることを示す重要な手続きです。これは重要な書類の取り扱いにおいて用いられるため、忘れないようにしましょう。
便箋の折り方と封筒への入れ方
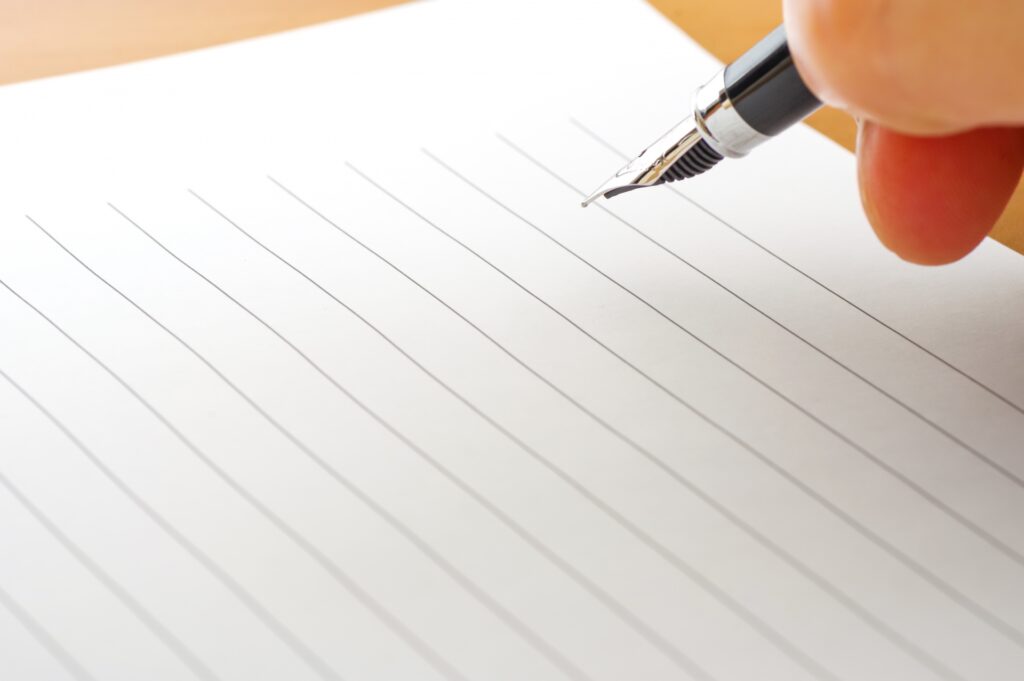
便箋を封筒に入れる際の折り方と向きには特定のマナーがあります。便箋は三つ折りにするのが一般的ですが、折る順序と封筒への入れ方にも注意が必要です。
初めに便箋の下部を3分の1の位置で折り、その後、上部を同様に折り重ねます。この折り方が適切です。
封筒に便箋を入れる際には、便箋の最初の文章が封筒の上部に来るようにしてください。この配置にする理由は、受け取った人が封筒を開けた時に最初に目にする部分が書き出しの文になるためです。これにより、メッセージをすぐに読み取ることができます。
教育実習のお礼状用便箋:縦書きの白色を選びましょう
ビジネスや正式な場では、便箋の色として白が基本とされます。適切なのは、縦書きでB5サイズの白無地、もしくは薄い縦罫線が入った便箋です。これらはどのタイプを選んでも概ね問題はありません。
ただし、便箋の白と封筒の白が異なると、急ごしらえのように見えてしまうことがあるので、両者の色が一致するよう注意が必要です。白い色味には多少のバリエーションがあるため、購入時には封筒と色を合わせることをお勧めします。
便箋を縦書きにする理由は、日本の伝統的な書き方が縦書きであることから来ています。正式な文書や公的な場では縦書きが好まれる傾向にあります。
教育実習のお礼状、手渡しもOK!その際の留意点
実習終了後に再び実習先を訪れる機会がある場合、お礼状を手渡しするかどうか迷うことがあるでしょう。もし後日、何かの用で実習先に行く予定があれば、その際にお礼状を持参しても問題ありません。
手渡しでお礼状を提出する場合、内容や形式は郵送する時と同様のマナーで準備することが一般的です。ただし、宛名の書き方には郵送とは異なる配慮が必要ですので、その点だけは注意が必要です。
手渡し時の宛名書き方:住所は省略可能
手渡しでお礼状を渡す際には、住所の記載は不要です。宛名には、実習先の学校名、先生のクラス名や役職、お名前を明記しましょう。
封筒の裏面には、自分の住所、大学名、氏名を記入し、さらにその日の日付を左上に加えることで完璧です。自己の情報を忘れると、お礼状をどなたから受け取ったのかが分かりにくくなるため、これらの詳細は確実に記入することが重要です。
教育実習のお礼状が遅れた場合の適切な対応

お礼状の送付が遅れてしまった場合でも、決して送らない選択は相手に対して非常に失礼にあたります。遅れたとしても、お礼状は必ず送るようにしましょう。
教育実習後のお礼状は、通常、実習終了後1週間以内、遅くとも2週間以内に送ることがマナーとされています。しかし、実習後に忙しいこともあり、お礼状をすぐに送れない場合もあるでしょう。
お礼状の送付が遅れる場合は、お詫びの言葉を添えることが重要です。例えば、「お礼を申し上げるべき時期を過ぎてしまいましたが、遅ればせながら心からの感謝を伝えたく、お詫びと共にお礼状をお送りします。」という形で、遅れた理由を丁寧に説明し、お詫びしてください。
教育実習のお礼状についての要点まとめ
- 白色無地の長形4号の二重封筒を使用することが望ましく、コストパフォーマンスに優れたもので十分です。
- 封筒の裏面には、自身の大学名、学部、および教育実習生であることを明記しましょう。
- 封筒をのり付けした後には、封筒に「〆」という封字を記入して正式性を示します。
- 実習後に実習先を訪問する場合、お礼状を直接手渡しすることも可能です。
- お礼状は通常、実習終了後1週間から2週間以内に送付するのが基本ですが、遅れる場合はお詫びの言葉を添えて送りましょう。
- 封筒選びは重要で、適切なものを選ぶことでこれまでの印象を損なわないようにします。
礼儀正しさや基本的な社会人マナーは教育実習でも非常に重要です。あなたが学校を代表する学生としてどのように振る舞うかは、将来的な実習生受け入れに影響を与えることもあります。
実習中の感謝の気持ちを適切に表現し、好印象を残して終えることが後輩への良い道を築くことにもつながります。最終日に向けた挨拶の準備も忘れずに、スムーズに表現できるように事前に準備しておきましょう。
この記事が、教育実習を気持ちよく終えるための参考になれば幸いです。