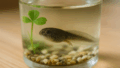「土用の丑の日」と聞くと、多くの人が夏にうなぎを食べる日というイメージを思い浮かべるでしょう。暑さが厳しい時期にスタミナをつけるためにうなぎを食べる習慣は有名ですが、そもそもなぜこの日なのか、また「土用」や「丑の日」という言葉にはどんな意味が込められているのかをご存じでしょうか?
この記事では、土用の丑の日の基本的な意味やその由来、うなぎが食卓に並ぶようになった歴史的な背景、さらにはうなぎが苦手な方にも楽しんでいただける代わりの食材まで、できるだけわかりやすく紹介します。初心者の方でも読みやすいように、関連する豆知識やちょっとした工夫も添えています。今年は少し知識を増やして、土用の丑の日をより豊かに味わってみませんか?
土用の丑の日とは?意味と由来を簡単に解説
「土用」とは、立春・立夏・立秋・立冬の前にあたるおよそ18日間の期間を指し、昔から季節の変わり目に体調を崩しやすいとされてきました。特にこの時期は、気温や湿度の変化によって体が疲れやすく、消化機能が落ちるとも考えられていたため、昔の人は特別な食事や休養を心がける期間と位置づけていました。例えば、胃腸に優しい食べ物を摂る、体を冷やさない工夫をするなど、生活全体で季節の変化に対応する知恵が受け継がれていたのです。
「丑の日」とは、十二支を日付に当てはめた際の「丑(うし)」に当たる日を意味します。十二支は本来、時間や方角、日付を表すためにも用いられ、暦の一部として活用されていました。したがって、「土用の丑の日」とは、土用の期間中で干支が丑に当たる日を示す言葉になります。これらの用語が合わさることで、季節と暦の知恵を組み合わせた日本独自の風習が形成されたのです。
「土用」も「丑の日」も、古代の暦と思想から生まれた言葉
古代の中国から伝わった陰陽五行思想では、自然界を木・火・土・金・水の5つの要素で説明します。土用の期間は「土」の気が強くなるとされ、この時期は体調が崩れやすいと信じられてきました。そこで、丑の日には「う」のつく食べ物を食べて元気を補う、という知恵が広まったのです。例えば、うなぎだけでなく、梅干しやうどん、うり(瓜)などもこの日に食べると良いとされ、地域によっては独自の食文化が発展しました。
また、土用は夏だけでなく、春・秋・冬にも存在します。特に夏の土用は暑さとの戦いになるため、「体をいたわる食事」が重視され、土用の丑の日が広く知られるきっかけとなったのです。
なぜうなぎ?平賀源内の発案と江戸時代の背景

うなぎを食べる習慣の由来には、江戸時代の発明家・平賀源内のアイデアが関わっているといわれています。夏場に売上が落ちて困っていたうなぎ屋に、「本日丑の日」と書いた看板を出すことをすすめたところ、大評判になったそうです。これがきっかけで、夏にうなぎを食べる習慣が全国に広まったとされています。
さらに江戸時代の庶民文化では、滋養のある食べ物としてうなぎが重宝されていました。当時の江戸は暑くて湿度も高いため、体力を消耗しがち。そんな中で脂ののったうなぎは貴重なエネルギー源となり、平賀源内の仕掛けも相まって人気を博したのです。
土用の丑の日は1回とは限らない?実は2回ある年もある
土用の期間は約18日間あるため、十二支の巡り合わせによっては「丑の日」が2回登場する年があります。この2回目の丑の日は「二の丑」と呼ばれ、昔から特別な意味を持つ日として知られてきました。二の丑がある年は、最初の丑の日とあわせて2回うなぎを食べる家庭も多く、夏の恒例イベントとして親しまれています。
また、1回目と2回目でうなぎの調理方法や付け合わせを変えて楽しむ工夫をする方も増え、両日をそれぞれ異なる味わいで満喫する方もいます。例えば、1回目は蒲焼きで定番の味を楽しみ、2回目はひつまぶしや白焼きなど、さっぱりした調理方法でバリエーションを加えるのも人気です。
2025年の土用の丑の日は 7月24日(木)と8月5日(火) の2回で、このタイミングを利用して夏のスタミナ補給や家族での食事会を楽しむ方も多いでしょう。複数回あることで、うなぎ料理だけでなく、旬の野菜や薬味を組み合わせたアレンジレシピを試す良いきっかけにもなります。
うなぎの栄養と夏バテ防止の効果
うなぎはビタミンA・B群・D・E、さらにカルシウムや良質な脂質が豊富で、健康維持に欠かせない栄養がたっぷり含まれています。これらの栄養素は疲労回復や免疫力のアップに効果があるといわれ、特に夏の暑さで体力を消耗しやすい時期にぴったりの食材です。また、うなぎに含まれるDHAやEPAなどの不飽和脂肪酸は、血流改善や動脈硬化の予防、美容効果や脳の働きをサポートする効果も期待されています。さらに、皮膚や粘膜の健康を維持するビタミンAや、エネルギー代謝を助けるビタミンB群が含まれているため、夏バテ対策として昔から重宝されてきました。
ただし脂分が多いので、食べすぎには注意が必要です。1人分の目安はうなぎの蒲焼きなら半尾程度とされ、食べすぎると胃もたれやカロリー過多になることがあります。適量を心がけるとともに、副菜には大根おろしや酢の物、さっぱりとした野菜の和え物など消化を助ける食材を添えると、胃腸への負担をぐっと減らすことができます。また、味の濃いうなぎにはきゅうりやトマトなど水分の多い野菜を組み合わせると、体をクールダウンさせる効果も得られます。
食べ方の工夫で体への負担を軽減
おすすめは、ひつまぶしのようにお茶漬け風にして、だしやお茶をかけてさっぱりと食べる方法や、白焼きにしてわさび醤油やポン酢を添えるスタイルです。お茶漬けにすることでうなぎの脂がほどよく落ち、消化にも優しくなります。
さらに、薬味や副菜に野菜をたっぷりと加えることで栄養バランスが良くなり、胃もたれせずに最後まで美味しくいただけます。たとえば、三つ葉や大葉、刻みねぎ、わさびなどを散らすと香りがぐんと引き立ち、食欲が落ちた時期でも口に運びやすくなるでしょう。きゅうりやトマトなどの冷たい野菜と組み合わせると、食感や彩りもアップして一層食卓が華やぎます。
また、電子レンジやグリルで温める際は、アルミホイルで軽く包んで蒸し焼きにすることで、ふっくらとした食感や旨味が増します。さらに少しお酒や出汁をふりかけてから温めると、風味が格段に良くなるのでおすすめです。こうした小さな工夫を取り入れることで、家庭でも料亭のような美味しいうなぎ料理を手軽に楽しむことができます。
うなぎが苦手でも大丈夫。“う”のつく食べ物で夏を元気に過ごそう
昔から「丑の日には“う”のつく食べ物を食べると良い」といわれてきましたが、この背景には、夏の暑さで弱った胃腸をいたわる知恵や、栄養補給のための先人の工夫が込められています。うなぎがどうしても苦手な方や、価格が高くて手が出しづらいという方には、手軽に取り入れられる他の“う”のつく食材がおすすめです。これらの食材も栄養価が高く、夏の疲れを癒すのにぴったりです。
- うどん:冷たくしても温かくしても美味しい万能メニュー。シンプルにざるうどんとして食べるのはもちろん、トッピングにネギや生姜、ミョウガをのせると風味が増し、夏バテ防止にも効果的です。ゴマや大葉を加えることで、香りや食感にアクセントが出て飽きにくくなります。
- うずらの卵:かわいらしい見た目でタンパク質もたっぷり。ゆで卵にしてサラダに添えたり、お弁当の彩りとして使うと子どもも喜びます。カレーや煮物に入れると、うずら特有のコクが料理全体に広がります。
- うめゼリー:爽やかな酸味で夏バテ防止に効果的です。手作りの梅シロップやはちみつを使えば優しい甘酸っぱさが楽しめ、冷やして食べるとデザート感覚でリフレッシュできます。小さなカップに分けて凍らせると、ひんやりとしたおやつとしても楽しめます。
- うに風味のふりかけ:少しの贅沢感でご飯が進むアイテム。炊き立てのご飯やおにぎりにまぶすのはもちろん、パスタに振りかけて和風スパゲッティ風にアレンジするのもおすすめです。手軽に“海の幸”の香りを楽しめます。
これらの食材をうまく取り入れれば、うなぎを食べなくても土用の丑の日を十分に楽しむことができ、栄養補給もばっちりです。
まとめ|「土用の丑の日」の本質を、今年は味わってみませんか?
土用の丑の日は、単にうなぎを食べるだけの日ではなく、古くから季節の変わり目を乗り越えるための知恵と文化が凝縮された特別な行事です。昔の人々は、この時期に体力や気力が落ちやすいことを知っており、栄養価の高い食材を積極的に取り入れることで健康を保ってきました。うなぎや「う」のつく食材には、暑さで疲れた体を癒す栄養が豊富に含まれており、家族や友人と一緒に楽しむ食事としても最適です。
今年は、うなぎを蒲焼きやひつまぶしで味わうだけでなく、冷やしうどんやうめゼリーといった代替メニューを組み合わせて、より幅広い料理を楽しんでみませんか?また、家庭での調理法を工夫することで、少しのひと手間でうなぎ料理の美味しさを一段と引き出すこともできます。
さらに、近年注目される資源保護の観点から、国産・養殖うなぎを選ぶ、食べ残しを減らす、植物性の代替食品を試してみるといった取り組みも大切です。こうした選択は、私たちの未来の食文化を守る小さな一歩にもなります。今年は土用の丑の日の背景にある意味や文化を意識しながら、家族や友人と健康的で環境にやさしい食卓を囲むひとときを過ごしてみるのも素敵ですね。